
介護の仕事は好き。でも職場の人間関係がつらい。
そんな悩みを抱えていませんか?
特に職員同士の関わりがストレスになり、辞めたいと思っている。
このように思ったことがある方もいるかもしれません。
・介護職で人間関係に悩んでいる人
・介護職で人間関係が面倒くさいと思っている人
・介護職に興味があるけど、何で人間関係が悪いの?
このような方へ向けた記事となっています。
介護職の転職原因1位は人間関係です。
「介護労働実態調査」というアンケートで、
介護労働者が直前の仕事を辞めた理由、第1位に挙がっている程です。
参照:令和6年度「介護労働実態調査」結果の概要について
私は10年近く、管理職をしていました。
その間、人間関係のトラブルは尽きたことがありません。
・AさんがBさんに対してだけ、挨拶をしない
・ドライバー同士で事務所でケンカをしていた
・Cさんが会社の悪口を言って、同意を求めてくるから困っている

このように介護職の職員同士の関わり方。
介護職の人間関係に悩む方へ向けて、よくある原因とその対処法を具体的にお伝えします。
そして、最後の手段は環境を変える、即ち異動や転職です。
でも、「今の環境を変える前に、自分でできることはある?」
そんなヒントを探している方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。
介護職の人間関係が悪い原因は3つ
介護職は、人間関係が悪い所が多いと聞きます。
つまり、働いている個人だけに問題があるのではないです。
介護職には、そうさせている環境があるといえます。
介護職の人間関係が悪いと言われている原因です。
・スタッフの負担が大きい
・派閥がある
・多様な職種による意識の違い
職員個人の性格が原因と言いたくなります。
しかし、その職員の欠点が出てしまう環境にも問題があります。
個人の性格や能力を原因にしては、なかなか解決できません。
人間関係を悪くしてしまう環境に原因を求めましょう。
介護職個人が、性格的に問題があるのだけではありません。
そうさせている職場にも問題があるといえます。

人手不足で職員のストレスが大きい
介護業界では、まだまだ人員不足があります。
職員一人ひとりの負担が大きくなると、精神的に余裕がなくなります。
余裕がないと人に対して、配慮ができなくなります。
そんな状況のなかで
・新人の育成まで手が回らない
・仕事の負担が不公平化していく
・肉体的にも精神的にも疲れてしまう
このような事態になります。
心が疲れてしまって、人にやさしくできますか?
難しいですよね?
そもそもの人員不足が、人間関係の悪さに拍車をかけている。
人間関係が悪くなる原因の一つです。
介護職は人間関係が閉鎖的

介護職は閉鎖的な人間関係があります。
なぜなら、介護職は異動が少なく同じ人間関係が続きやすいからです。
異動がある事業所でも、パートの職員は異動がないですよね。
何年も働いているパートの人が数人いても、閉鎖的な環境はできやすいです。
・職員間でコミュニティが形成される
・ベテランの職員が現れ、お局的な存在になる
・結束がある反面、排他的になる
私がデイサービスの管理者をしていた時には一人、お局的な人がいました。
その方は、開設時代からのベテランです。
パートで異動がなく、昔を知っているた方で厄介な存在でした。
・新しく入ってきた人に、会社の悪評を言う。
・自分の思うように仕事をするために、味方を増やす
・数人で結託して、会社の方針に反抗する
文句は言っているのですが、辞めないんです。
なぜなら経験を積んでいる分、集団の中心になれるからです。
お局的な存在の職員が、自分の味方になる人を集める。
それが派閥になります。
良くない派閥では、会社の悪口や仕事の愚痴が多くなります。
そして、雰囲気が悪くなってしまうのです。
介護職は人間関係が閉鎖的になりがちです。
その結果、職場の雰囲気や人間関係がわるくなる傾向にあります。
色々な立場(多職種)の職員がいる
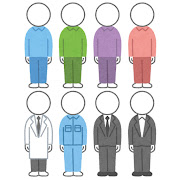
多職種がそれぞれの立場で意見を言う。
その時に、摩擦が生じてしまうのも人間関係を悪くする原因となります。
介護職には、有資格者を含めて色々な人が携わっています。
介護職以外にも、看護師や理学療法士、ドライバーなど様々です。
そして、仕事への価値観も多様になります。
看護師としての利用者へのかかわり方と
ドライバーの利用者へのかかわり方は当然、違ってきます。
看護師は、疾患に対するリスクを中心に関わります。
・糖尿病の型の低血糖症状
・脳梗塞の利用者の再発の兆候
・心疾患を持っている方の呼吸や胸の違和感
ドライバーとして働いている人は、その目線は持てないのです。
医療や介護の経験が少ない、そのような方が多いからです。
しかし、送迎という仕事を通して独自の視点を持っています。
・住宅環境や、利用者の生活をみることができている
・利用者の家族との関わりがあり、家族環境を知っている
・車という空間により、利用者から相談を受けやすい
このようにそれぞれで目線が違うのです。
そこでコミュニケーションが円滑でないと、不信感につながってしまいます。
多様な働き方をしている人が集まっている。
上手くいくと、チームとして視野を広く持てる職場になります。
しかし、介護職ではついコミュニティが閉鎖的になりがちです。
その結果、摩擦がおきて人間関係が悪くなってしまいます。
では、どう解決していきましょうか?
人間関係のストレスへの対処法は境界線と発散
人間関係のストレスへの対処法は、「境界線」と「発散」。
つまり、次の2つが大切です。
・適度な関係性を保つこと
・ストレスをため込まずに外に出すこと
人はストレスを感じるとき、たいてい「思い通りにいかない」と感じています。
それは、理想と現実のギャップに心が揺れる瞬間です。
そんなときに大切なのは、
・自分がその状況をどう受け止めるか
・抱え込まず、うまく発散できるか
この2つが、心のバランスを保つポイントになります。
ここからは、具体的に3つの対処法に分けてご紹介します。
相手を受け容れてストレスを和らげる

相手を受け容れて、認めることで
ストレスになっている職員への捉え方を変えます。
受け容れるとは、
・そんな人もいるよね
・そんな考え方もあるよね
と認めることです。
「介護職は利用者のために働くべきだ」
「利用者の愚痴を言うのはよくない」
など、自分の考えを相手に求めない。
まずは相手の立場になって考えてみることです。
・お金のため、生活のために仕事をしている人もいる
・愚痴を言うのは、精神的につらいのかな?
といった感じで、少し相手の立場を考えます。
決して共感したり、自分の考えを抑えたりしなくて良いです。
「人は人、自分は自分」相手を認めるけど、自分も認める。
相手と自分とのボーダーラインをはっきりさせておく。
そうすると、受け容れられるようになります。
相手を受け容れると、少しずつストレスの度合いも変わってきます。
いつもと違った視点で、ストレスとなる人を受け容れてみましょう。
ただし、損得が絡んでくると難しくなります。
距離が近くて、ボーダーラインが引けない状況です。
そんな時は距離を置きましょう。
距離を置いて人間関係を変える
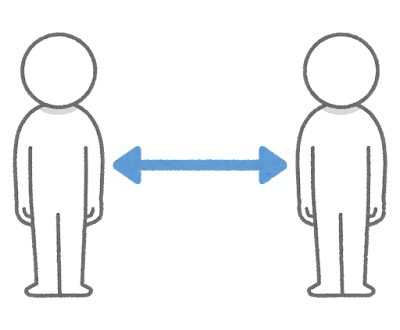
ストレスを減らすためには、職員と物理的にも精神的にも距離を置きます。
あくまでも、仕事の関係であると割り切りましょう。
・距離を置くって、どういうことなの?
・職場では毎日、顔を合わせちゃうよ・・。
そうですよね。
イメージがわかないし、嫌でも関わってしまう現実があります。
そんな時は、業務時間以外で関わらないことです。
私の職場では、愚痴や悪口を吹聴するスタッフがいました。
しかたなく同調していた人が、だんだんとストレスが溜まっていったのです。
そこで、その方がとった行動は
・昼休みは外に出て休憩をとる
・一緒に帰らない
・職場でよく話す人を変える
など、ストレスになる人と一緒の時間を減らしました。
ポイントは、業務以外の時間で一緒に行動しないことです。
仕事上ではある程度、話をしていますがそれ以外は話さない。
このように距離を置きました。
そうすると、物理的にも精神的にも距離をおけます。
つまり、仕事上だけ関わる。
そうすると、距離を置けます。
ストレスは抱え込まないで相談する

人間関係のストレスは1人で抱え込まないで、相談しましょう。
相談相手は上司や同僚です。
・状況を解決してほしいときは上司へ
・メンタルを安定させたいなら、共感してくれる同僚へ
このように相談すると良いです。
・体調やメンタルが限界になりそう、
・このままでは「辞めたい」と思ってしまう
こうなったら上司へ相談です。
シフトの調整や、配置換えなど環境を変える対応をしてもらいましょう。
大きな施設であれば、配置換えして環境を変えることも可能です。
上司への相談については、次の記事に紹介してます。
相談しても対応してくれるか不安だ。
そう思ったら、参考にしてみてください。
同僚へ相談して、共感や賛同してもらえればメンタルを安定させられます。
人間関係のストレスは簡単に解決できないです。
少しでも気持ちの整理や、心のケアをしたいときには誰かに話しましょう。
1人で悩んでいると、よりストレスがかかります。
上司や同僚だけではなく、友人でも良いです。
まずは誰かに相談しましょう。
介護職の人間関係に限界なら異動か転職
人間関係のストレスに、限界を感じたら環境を変えてもいいです。
具体的手段は、「異動」か「転職」です。
・職場内でシフトの調整や配置を変える
・転職して、職場自体を変える
このように積極的に環境を変えて、関わる人を変えていきます。
あまりにもつらい状況であれば逃げていいんです。
あなたは十分に頑張りました。
では、どんな状態だと環境を変えるべきか?
まずは、環境を変える目安から伝えますね。
人間関係という環境を変える目安
環境を変える目安は何か?
どんな状況だと環境を変えるべきか?
それは自分が限界を迎えたとき、迎えそうな時です。
特に限界を迎えそうなサインには、いち早く気付いてあげましょう。
行動や考え方、体調が以前よりも変化が出てきた時が限界のサインです。
・眠れない、休みの日にタップリ寝ても足りない
・好きなことに興味がわかない
・過度に甘いものを食べてしまう
このような時は、ストレスの適応が難しくなっているサインです。
少しでも兆候があるときは環境を変える方向へシフトしましょう。
限界を迎えた時には、すでに手遅れです。
ストレスに対して限界を迎えたり、迎えそう。
そんなサインが自分の中にあったら、今の環境を変えましょう。
今、働いている職場がすべてではありません。
限界を感じたら、環境を変えましょう。
具体的手段は、「異動」か「転職」です。

異動で環境と人間関係の関わり方を変える

組織が大きい法人や会社であれば、他部署への異動を希望しましょう。
今ある人間関係を変えられます。
介護の仕事でも、職種が違えば人とのかかわり方も変わります。
・施設型
・通所型
・訪問型
など、施設のタイプで働き方が変わってきます。
そして、周りの職員との関り方も変わります。
例えば、デイサービスなどの通所型は、多職種との連携が必要になります。
看護師やドライバーなど、周囲とのコミュニケーションも大切です。
通所型の関わり方
メリット:チームとして一体感をもって仕事ができる。
デメリット:他のスタッフとの関りが濃いため、人間関係のストレスが発生しやすい
訪問型のサービスでしたら、自宅に基本は1人で仕事をします。
もちろん、サービス提供責任者や他事業所との連携は必要です。
それでも他の職員とは、一定の距離があります。
訪問型の関わり方
メリット:他の職員と、利害関係が無い距離感をもって関われる
デメリット:利害関係が無い分、困っても自分から働きかけないと協力が得にくい
他のスタッフとの人間関係が苦手な方は、自分に合った働き方を探す。
それも選択肢の一つです。
・転職でも、他職種へ行くのは変わらないんじゃないか?
・転職の方が人間関係も大きく変わるし、キャリアアップにもならないか?
そう思った方もいるかもしれません。
しかし、他職種で経験を積もうとすると、転職では採用のハードルが上がります。
なぜなら即戦力を求められているからです。
人間関係のかかわり方を変えて、新たな職種で働きたい。
そんな時は、まず転職よりも部署異動をして働き方を検討してはどうですか?
幅広く事業を行っている組織では、部署異動して環境を変えられます。
上司に相談して、希望してみましょう。
人間関係を変える最後の手段は転職

人間関係のストレスで、最後の手段は転職です。
人間関係を変えようとあれこれ行動しても、相手や周囲の環境は簡単に変わりません。
その中で、もうこれ以上耐えられない。
そうなったら転職して人間関係をリセットです。
人間関係の原因は、そこにいるストレスになる人だけではありません。
そんな人を採用した職場にも原因があります。
・人が少ないから採用基準が甘くなる
・介護職にあっていない人が採用される
・人間関係がおかしくなる
こういった負のループになっている職場もあります。
これ以上、耐えられない。
そして、組織も変わる気配が全くない。
そんな時は転職です。
今の職場からは去りましょう。
転職への準備は、以下の記事を参考にしてみてください。
介護職の人間関係によるストレス:まとめ
介護職に限らずですが、働く上での人間関係は重要です。
人間関係のストレスについて、原因と対処法をお伝えししてきました。
原因は次の3つです。
・スタッフの負担が大きい
・閉鎖的な環境
・多職種が関係する職場である
介護職では、どうしても人間関係が悪くなってしまう環境にあります。
また人間関係のストレスは、誰にでも起こり得るものです。
そして、人間関係のストレスでできる対処法は次の3つです。
・相手を受け容れる
・相手と距離を置く
・相談する
どうしてもつらいときは、
「異動、転職で環境を変える」選択肢もあります。
逃げることは、決して悪いことではありません。
あなたが心穏やかに働ける環境を見つけることが、何より大切です。
あなたが笑顔で働ける場所に出会えるよう、心から願っています。
ちなみに、ストレスそのものを解消する記事もあります。
ぜひ読んでみてくださいね。
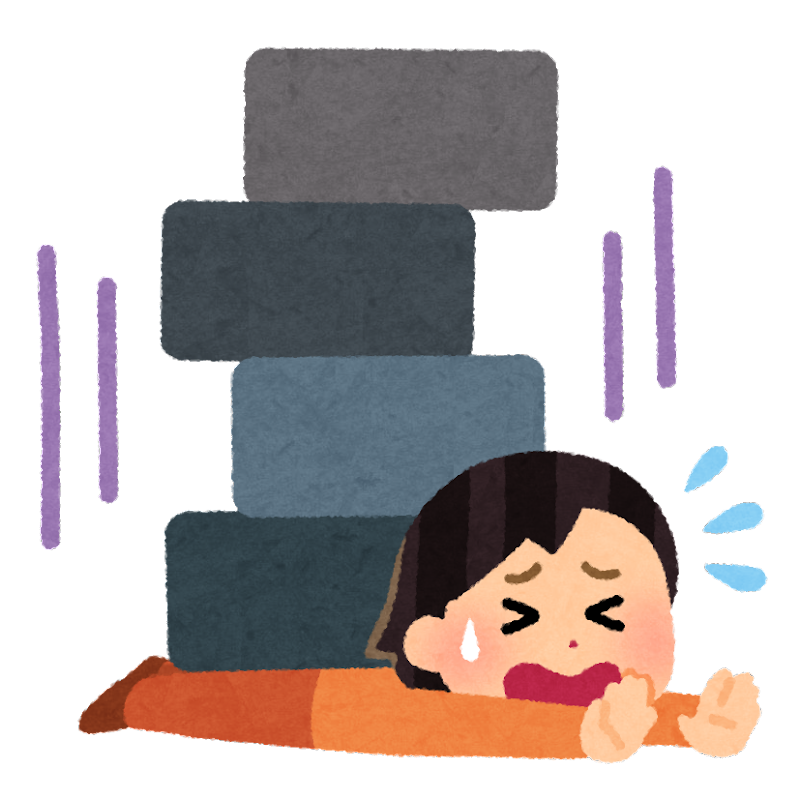

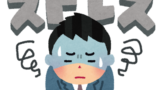

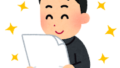
コメント