「利用者が亡くなったとき、どう向き合っていいがわからない。」
介護職では、利用者の死に直面するときがあります。
そんな時に
- 利用者が亡くなって、なかなかショックから立ち直れない。
- これからターミナルケアに関わるけど、どう向き合っていいか不安。
- 利用者が亡くなった後の喪失感から抜け出せない。
本記事では、死生観を形成して利用者の死を、どう乗り越えるかを話していきます。
私は療養型医療施設で、何度も患者が亡くなる経験をしてきました。
何人もの方の、亡くなった後のケアも行ってます。
昨日まで談笑していた方が、翌日には意識がなくなり、その日のお昼には亡くなられたこともありました。
あまりのあっけなさに、そのことを受け容れられませんでした。
・どうしても仕事として割り切ることができない。
・信頼関係をつくれた方が亡くなって、喪失感から抜け出せない。
社会人1年目の私としては、
このような気持ちにもなりました。
利用者の死に向き合うことは、単に喪失感や悲しい感情に対処するだけではないです。
これから家族など、身近な人が亡くなることが誰しもあります。
そのような時にも、きちんと向き合うことにつながります。
今回の記事を読んで人の死に対して、きちんと考えるきっかけとなれば幸いです。
利用者の死を乗り越えるために必要なのは、「適度な距離感」です。
そしてその中で、死や生に対する考え方(死生観)を持つことです。
そのために、できることを3つにまとめました。
- まずは「死」を忌み嫌わないこと
- 亡くなったことをどう受け止めるかを考える
- そして、向き合うためには死を目の当たりすること
まずは適度な距離感とは何なのか?
そして自分の死生観を持つ方法をお伝えします。

死生観としての「適度な距離感」とは2.5人称
まず、利用者が亡くなったときには、他人事でもない家族のように近すぎない「適度な距離感」が必要です。
では「適度な距離感」とはどれくらいのイメージでしょうか?
死の人称といわれる表現では、1人称~3人称とあります
その中で2.5人称くらいが、ちょうど良いです。
(ノンフィクション作家の柳田邦男さんが提唱しています)
医療従事者は通常3人称で、2人称である患者さんの家族にはなれません。
引用:メディカルノート「がん患者さんに2.5人称の医療を。サイコオンコロジーで出会った患者さんから学んだ「人の持つ力」」
柳田氏が推奨されている「この患者さんが自分の家族だったらどうするか」というふうに
患者さんにもう一歩歩み寄って考えるのが2.5人称の医療です。
近すぎるとうつ状態になってしまったり、バーンアウトしてしまったりします。
かといって他人事としてとらえすぎると、あまりにもドライというか冷たい対応になります。
例えば、事故が起こって目の前に助けなければいけない人がいました。
自分がどこのポジションにいるかをイメージしてみましょう。
- 友人や家族が被害者であり、目の前の出来事にショックを受けて、ただうろたえてしまう。
- 目の前の人を助けようとして、今、できることをしようと行動する。
- 他人事としてとらえ、事故の状況をスマホのカメラで撮影する。
とらえ方としては、2ですよね?
つまり利用者が亡くなられたときに、うろたえないこと。
職員としてできることを行ってきたのか、を考えられるかどうかです。
また、突然に利用者の急変を目の当たりにしたときに、冷静に行動できるかです。
では適度な距離感をもてるために、必要な考え方や経験を挙げていきます。
利用者の死を避けたり、忌むことをしない
まずは人の死に対して、避けて通ったり忌み嫌うことをしないこと。
そして積極的に学ぶことが大切です。
そもそも日本において、死ぬことが「不幸」と表現されるように忌み嫌うこととされています。
誰もがいつかは死ぬのに、かかわることを避けようとします。
避けていても、いつか利用者が亡くなったり、身近な家族が亡くなる現実に直面します。
その現実を前に、大きな精神的ショックを受けてしまうだけになってしまいます。
そうならないために
・「死」に対して専門職として学ぶ
・仕事で利用者が亡くなる出来事を避けない
つまり知識として向き合い、経験していくことです。
そして大事なのは、避けたり関りを拒否しないで、いつか来ると受け容れることです。
「死」に対して学ぶ
避けない、そして忌むことをしないためには積極的に学びましょう。
死生観や終末期ケア、緩和ケアなど学べることはたくさんあります。
まずできることは、
・死ぬことに対しての関連する本を積極的に読むこと
・看取りを経験した人に直接、話を聴く
・人生会議などの、集まりに参加してみる
少しでも向き合って、「死」に対して触れることです。
そして徐々に受け容れられるようにしてみることです。
例えば、終末期ケアについて体系的に学べる方法のひとつが、資格取得です。
終末期について学べる、終末期ケア専門士という資格があります。
資格取得のメリットとして
・ターミナルケアに対して幅広い知識を習得できる
・会員同士のコニュニティーがあり、意見交換ができる。
特に、資格取得後に会員同士のコミュニティで意見交換ができることは大きな学びです。
資格取得がゴールではなく、むしろ成長できるスタートになります。
興味のある方はこちらから調べてみて下さい。⇩
一般社団法人日本終末期ケア協会が開催している、終末期ケア専門士試験対策WEB講習会の案内です。
「死」に対しての捉え方は個人の経験や価値観によっても変わります。
どれが正解とは一概に言えないです。
まずは積極的に学んで、自分なりの価値観を持てる準備をしましょう。
受け容れるためには避けない
これまで医療や介護の仕事に関り、急変も経験しました。
なぜか患者や利用者が亡くなること、急変することを避ける職員が意外と多いです。
私が病院勤務の時代には、急変を避ける医者や看護師、介護士がいました。
急変が起き、患者の心臓が止まりかけている時に、
「5時なので私はもう、帰ります。」
そう言って、去っていった医者もいました。
利用者の死を避ける方法として、デイサービスへの転職を勧める意見もあります。
しかしデイサービスでも、急変の可能性はついて回ります。
デイサービスの看護師には、救急搬送や急変を嫌がる人もいました。
その結果として
・血圧が高い人に、執拗なバイタル確認を行う
・すこしでも体調がすぐれない利用者を、一方的に帰らせようとする
・何度も「具合が悪くないですか?」と聞いてしまう
かえって、利用者を不安にさせるような行動が見られました。
利用者が急変することや、亡くなることを避けてばかりでは向き合えません。
介護職・医療職は、利用者・患者が亡くなることに、心の準備をしておくべきです。
死を乗り越えるために、どう受け止めるのか
誰もがいつかは死にます。
絶対に避けることはできないです。
だから、それをどう乗り越えるのかが大切です。
避けることができないからこそ、どんな最期を迎えるかが大事になります。
利用者が亡くなられた時の受け止め方によって、気持ちは変わってきます。
死生観には、死の受け止め方として「死の人称」があります。
・1人称(利用者自身)
・2人称(家族)
・3人称(自分自身)
それぞれの立場から考えてみましょう。
利用者自身にとってどうだったのか?【1人称】
利用者との死に関わるときに、亡くなったことはショックですよね?
でも、目を背けないで、利用者にとってどんな最期だったのか。
1人称で、しっかり向き合ってみましょう
・最期を迎えたとき、どんな状況だったのか?
・誰がみてくれていたのか?
・理想とする最期か、そうではなかったのか
自分事として考えることです。
そうすると今後、関わる利用者の、最期を考えて行動できるからです。
人が亡くなることを正確に予測することは、不可能です。
突然に最期を迎えたとしても、本人にとってどうだったのか?
しっかりと1人称として、捉えて考えましょう。
ご家族にとって、どうだったのか?【2人称】
ご家族にとっては、とてもつらい気持ちになります。
2人称として、どんな気持ちなのかを寄り添って考えてみましょう。
利用者が亡くなって、一番ストレスを受けるのは身近な家族です。
・生前に、できることはできたのか
・心残りは何だったのか
・今、どう感じているのか
機会があるのであれば、ご家族から話を聴いてみましょう。
傾聴することで、ご家族の心の負担を減らす支えにもなります。
利用者が亡くなったときに、一番に死を感じるのは何よりも身近な家族です。
2人称としての感じ方、捉え方は家族の立場として考えることです。
そして自分はどうだったのか?【3人称】
そして第3者として、自分自身はどう感じたのかを向き合ってみましょう。
今の介護職としての立場で十分です。
・しっかりできたことは何なのか
・もっとこうすれば良かったことは何か
・今回のことで、得られたものは何か
そうすると、これから利用者にどう関わっていくか考えられます。
ちょっとでも良いです、前向きに考えて進みましょう。
最初は冷静に考えられないかもしれません。
できる範囲で良いので、しっかり向き合いましょう。
第3者という、3人称として冷静に捉えることも大切です。
死を目の当たりすることで死生観を育む
何よりも経験すること
人間の、最期の迎え方についての考え方は、多くあります。
本などで勉強することや、日ごろから考えることはとても大事です。
そして何よりも経験することで学べます。
何ごともそうですが、経験でしかわからないことがあります。
介護の仕事で、いつか利用者が亡くなる時を目の当たりすることがあります。
その時にはしっかりと向き合っていきましょう。
最初は喪失感のほうが大きいかもしれないです。
でも時間とともに受け容れられ、そして向き合うことができます。
向き合い、受け容れられることができれば、適度な距離感を感じられます。
利用者の死に向き合うためには、
なによりも経験し、目の当たりにして学ぶことです。
自分なりの死生観に、結論や終わりは出せない

人として、最期を迎える時の考え方は、一朝一夕で結論が出るものではないです。
経験をしっかりと重ねていきましょう。
そこから、あせらずにゆっくりと自分なりの価値観を築き上げていきます。
死に対する価値観は全員が、誰もが納得できる正解がないからです。
人それぞれに考え方があり、どれもその人にとっての正解といえます。
そしてそれはその人の経験や学んできたことから得られたものです。
それくらい簡単に答えが出せるものではない、ということです。
私自身も療養型医療施設にて、何度も患者が亡くなる場面に立ち合いました。
その中には、いろいろな最期の迎え方があります。
天涯孤独で、誰も悲しむ人がいないまま亡くなっていく患者をみたことがあります。
その時に、その方の人生の最期をみていたのは、私一人でした。
その時、この人にとって、人生の最期はこのような形を望んでいたのか?
ふと、そんなことを考えて、仕事をしていました。
そのように自分なりの疑問を持ちながら、経験を重ねていくこと。
それが自分なりの価値観につながります。
⇩1人のご利用者の死から学んだ経験を綴りました
利用者の死を乗り越えるために:まとめ
どうでしょうか?
利用者が亡くなることについて、ショックを受けすぎないためには
「死生観」をもつことと、
「適度な距離感」が必要になります。
そのためには
・まずは「死」を忌み嫌わないこと
・亡くなったことをどう受け止めるかを考える
・そして、向き合うためには死を目の当たりすること
それを積み重ねて、自分なりの価値観を築き上げていくことができます。
そして、2.5人称の家族と他人の中間くらいの距離感を保っていきましょう。
人が亡くなることに対してをテーマとすることは、不謹慎と思う方もいるでしょう。
しかし、この避けて通れないテーマにはきちんと向き合って、考えることが大切です。
「死」に対しては忌み嫌うことをしないで、きちんと向き合っていきましょう。
利用者の死を乗り越えられると、人として大きく成長できます。
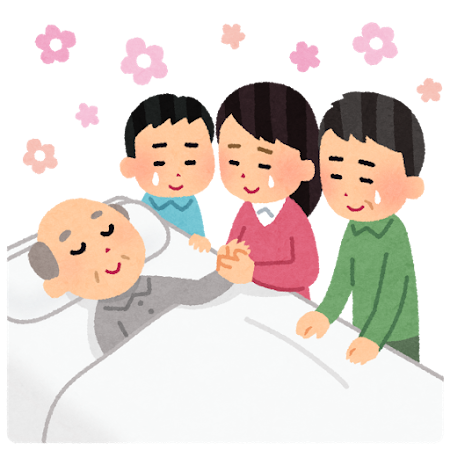



コメント