
お疲れ様です。
今回はデイサービスなどでの、送迎時の介助についてです。
送迎で、利用者の介助や自宅内まで送っていいのか?
迷ってしまったことはないですか?
・送迎で家の中まで介助しているけどいいの?
・迎えの時に、着替えを手伝っているけど、どこまで介助していいの?
・施設からは玄関までといわれたけど、部屋まで送らないと心配
送迎で、利用者の介助の迷ってしまうスタッフが少なくありません。
特に家の中に入っていいのか?
どの場所までが許されるのか、判断に迷ってしまいます。
送迎について、介護施設がする対応は次の3つになります。
・送迎はどこまでするべきか具体的な定義はない。関係者でしっかり決める。
・施設がどこまで送迎するのかを確認し、一度、ルールを徹底する。
・送迎時の送り出しのヘルパー、通所サービスにある居宅内介助を利用する。
つまり現場で決めて、関係者で共有する。
必要であれば、他のサービスを利用する。
ということです。
制度と実例を交えて解説していきます。
送迎は範囲は?実は具体的な定義はない
まずは、デイサービスなどの送迎がある施設が、どこまで送迎をするのか?
デイサービスの送迎業務の範囲は「居宅の玄関まで」とは定義されていません。
はっきりと答えているのは、「居宅まで行くことが原則」です。
つまり「居宅に帰着し安全な状態と認められるまで」です。
ドアTOドアで玄関まで、といった決まりはないです。
自宅内に入ってはいけない、といった情報を聞いたことがあるかもしれないですね。
しかし厚労省からは、はっきりと定義されていません。
Q送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても差し支えないか。
厚生労働省:介護サービス関係Q&A週
A居宅まで迎えに行くことが原則である。ただし、道路が狭隘で居宅まで送迎車が入ることができない場合など、地理的要因等から妥当と考えられ、かつ、利用者それぞれに出迎え方法を予め定めるなどの適切な方法で行う必要がある。
よく聞かれる、ドアTOドアの意味は、安全な状態から安全な状態です。
「玄関まで送ればそれでいい」ではありません。
まして、家の中に入ってはダメ、とは一言も発信がないです。
あくまで「居宅に帰着し安全な状態と認められるまで」です。
では、どのように判断をしましょうか?

送迎の範囲は「人によって変わってくる」
「安全な状態」とはどんな状態なのでしょうか?
安全な状態は、利用者によって違ってきます。
よって、きちんと利用者ごとに関係者で決めておく。
このような判断が求められます。
歩ける人にとっては、自宅の中に入ってしまえば大丈夫でも、
車いすの人にとっては、ベットまで行く必要がある場合も考えられます。
つまり、「利用者それぞれに出迎え方法を予め定めるなどの、適切な方法で行う必要がある」です。
(厚労省はこのような、ボヤっとした発信しかしてません)
人によって「安心・安全」な場所は違います。
重要なのは利用者や家族、ケアマネ、施設の管理者、送迎担当者で事前に決めておくことです。
その人にとっての適切な場所を、よく検討しましょう。
そして、ケアマネにはプランに記載することを伝えます。
では介助内容はどこまでできるのでしょうか?
送迎時の介助はどこまで可能?
例えば、家の中まで送るとします。
さらに家の中の介助内容は、どこまでするべきか?
はっきりとした線引や明記はされていません。
これもまた、人によって違ってきます。
居宅内介助について、厚労省のQ&Aでは、次のように発信しています。
通所介護等の居宅内介助については、独居など一人で身の回りの支度ができず、介助が必
厚生労働省:平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A ( 平成27 年4 月1 日)※問番号52
要となる場合など個別に必要性を判断の上、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置
付けて実施するものである。
現在、訪問介護が行っている通所サービスの送迎前後に行われている介助等について、一
律に通所介護等で対応することを求めているものではない。
例えば、食事介助に引き続き送迎への送り出しを行うなど訪問介護による対応が必要な利用者
までも、通所介護等での対応を求めるものではない。
つまし必要があれば、計画に明記すれば可能ということです。
・関係者で、個別でどこまでの介助が必要か判断する。
・判断したら、ケアマネジャーや施設、家族や利用者で一律に決めておく
・何らかの変化や問題があったら、関係者に報告、連絡、相談する
この繰り返しです。
しかし決めておいても、状況は常に変わります。
変わったときには、すぐに報告です。
送迎のスタッフは、介助内容に少しでも変化があったら報告

送迎を担当しているスタッフは、介助内容にちょっとでも変化があったら報告です。
気が付いたら介助する範囲が変わっていた。なんてケースもあります。
・利用者の体調は常に変わるので、徐々に介助量が変化していく
・家族の要求が現場で、増えていく
・現場のスタッフが良かれと思ってやってしまう
このように利用者の体調、周囲の環境は刻一刻と変わります。
・必要以上の支援をしていないか?
・あるいは介助量が不足していないか?
・送迎の担当者によって、介助量が変わってないか?
気が付いたらすぐに報告して、施設で送迎方法を検討しましょう。
現場の介護職員はその利用者の状態を一番、知っています。
少しの変化にも気付たら、すぐに報告が必要です。
それはトラブルを避けることにもなります。
送迎時のルールを決定したら周知と記録の徹底
・送迎は必要によっては自宅内まで行う
・自宅内の介助も、個別で必要な範囲を判断して行う
ここまで送迎時の介助できる範囲について確認しました。
介助方法について決めたら、絶対に必要なのが
・関係者できちんと決めて、全員に周知しておく
・決めた内容について、きちんと記録として残しておく
この2点です。
行っていないと利用者に被害が及んだり、現場のスタッフがクレームを受けたりします。
利用者や職員を守る意味でも、しっかりと実施しましょう。
送迎内容の周知が足りないトラブル
決めた介助内容が周知されていないと、トラブルになります。
・真っ先に利用者に迷惑をかける
・知らされていない担当者が、クレームを受けてしまう
利用者だけではなく、職員の不信感にもつながります。
私が送迎で、マンションに住んでいる方の送迎をした時の話です。
利用者のマンション近くまで着くことはできました。
しかしマンションには駐車場がなく、車を停める場所がなかったのです。
そして、どこに停めていいかわからず、マンション周りをウロウロしてしまいました。
さらに施設に電話をしてもなかなかつながらず、確認にも時間がかかったのです。
実際はわかりにくい場所に停めるよう、利用者からは指定されていました。
しかし、私には知らされないまま、送迎だけ任されていたのです。
何とか連絡がとれ、迎えには行けました。
しかし、迎えに行ったご利用者からは「遅い!」と怒られ
車に乗っていたご利用者は、施設についたら疲れきってしまいました。
疲れたご利用者は、施設に着くと横になってしまい、本来のサービスが受けられなくなってしまったのです。
このように関係者全員に周知しないと、現場にいる利用者と職員が被害を受けます。
当たり前ですが、取り決めた介助内容は全員に周知しましょう。
関係者全員に周知するのは、当たり前ですが意外と抜けることが多いです。
忘れずに周知しましょう。
送迎記録を残して自分たちも守る
介助方法の取り決めや全員に周知ができたら、記録に残しておきましょう。
きちんと決めた詳細な介助方法を、忘れないためには重要です。
また、後日にトラブルへ発展しないための、確認や証拠にもなります。
・どこまで送迎を行うか
・どのような介助方法を行うか
・それをいつ決めたのか
・いつ全員に周知したのか
当たり前に思えますが、できずに口頭での周知で終わるパターンが往々にしてあります。
例えば、
マンションに住んでいる方で、エントランスまでは家族が送り迎えをしていたとします。
しかし、家族の体調の変化により、部屋までの付き添いが必要になります。
そんな時に、変わったことを担当者が報告します。
そこで、確認できる記録を取っていないとどうなるでしょうか?
担当していないスタッフは、忘れてしまう可能性があります。
新しいスタッフが入ってくると、知らないスタッフも出てきます。
そんな時に最初の担当者が辞めてしまって、新しいスタッフが担当したとします。
周囲のスタッフに聞いたときに、聞かれた人の記憶が曖昧だったらどうなりますか?
「確か、エントランスまでじゃなかったっけ?」
このように答えてしまったら?
言われた通りに行動しますよね?
その結果、何か事故が起こってしまうことがあります。
そうならなくても、家族からクレームを受けます。
担当した職員も、被害者となってしまいます。
口頭だけで伝えて、記録などの形に残さない。
それは絶対に避けましょう。
・介助方法の再現性をきちんとする。
・自己防衛としての確認と証拠にする。
このような観点からしっかりと記録を残しておきましょう。

訪問介護で送迎の送り出し
通所サービスの送迎で、できる介助には限界があります。
何もかも受ける必要はありません。
このような状況でしたら、送り出しや迎えのヘルパーを利用しましょう。
送り出しでヘルパーができる仕事は以下です。
・食事や服薬の介助
・排泄の介助
・身支度のサポート
・戸締まりの確認
・デイサービススタッフに引き継ぐまでの移動介助
送迎では、乗り合わせの方もいます。
次の家で待っていらっしゃる方もいます。
1人に過剰な時間がかけて、他の方に迷惑をかけてしまっては本末転倒です。
頼まれる介助量が、限界を超えているならば訪問介護の利用です
具体的に何が必要なのかを確認して、管理者や生活相談員へ提案してみましょう。

送迎時の居宅内介助というルール
現状では、送迎時に職員がベットサイドまで送っているケースもある。
しかし、その時間はサービス時間として認められていない。
そんな送迎時間を、サービスの時間(計30分まで)として認められるルールです。
送迎時に実施した居宅内での介助等(着替え、ベッド・車椅子への移乗、戸締まり等)に要する時間は、次のいずれの要件も満たす場合、1日30分以内を限度として、通所介護を行うのに要する時間に含めることができる。
参考:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)
① 居宅サービス計画及び通所介護計画に位置付けた上で実施する場合
② 送迎時に居宅内の介助等を行う者が、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者、介護職員初任者研修修了者(二級課程修了者を含む。)、看護職員、機能訓練指導員又は当該事業所における勤続年数と同一法人の経営する他の介護サービス事業所、医療機関、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員としての勤続年数の合計が3年以上の介護職員である場合
つまりは以下のような場合は、自宅内の介助時間をサービス時間として認められる。
ということです。
・利用者個別で独居や身体機能的に、介助が必要であると認められた時
・ケアプランや計画書に盛り込まれている
・介助する人も規定に該当する者であること
このルールで、ご家族への負担や経済的な負担が減らせるようになりました。
自宅内での介助時間を、ご利用時間の一部として捉えるルールです。
要はあいまいだった自宅内の介助を、
・家族が無理に時間を調整して行っている
・サービス外で、デイサービスの職員が行っている
という状況から
・デイサービスでも、自宅内の介助をサービスの一環として行えるようになった
・訪問介護を頼むほとでもない方の、自宅内の介助をお願いしやすくなった。
この方法では、介助に時間がかかる利用者を別で送迎時間を作って送迎することになります。
そして、居宅内介助は義務ではないので、デイサービスによってはできない所もあります。
いくつかの基準もあるので、算定可能か検討する
そして、人員や時間が取れるのか、事業所として検討する必要があります。

まとめ:送迎時の介助は「現場で決めて、記録して守る」
送迎がどこまでやっていいの?
そんな疑問に対して答えてきました。
・どこまでという決まりはなく、関係者で決める。
・変化があったらすぐに報告して方針を決めて、周知と記録
・訪問介護や居宅内介助を利用する
この3点です。
送迎を具体的にどこまでするのかを
法令で決められてはいません。
結局は現場の判断に任せられています。
施設として、一人一人の送迎について、しっかり取り決めておきましょう。
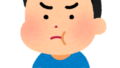

コメント