
介護職は.、コミュニケーション能力を求められる仕事でもあります。
身体介助だけでなく「心のケア」が求められることも多いからです。
利用者と楽しそうにコミュニケーションがとれない
もともと人見知りで、コミュニケーションが苦手
コミュニケーションの取り方がわからず、つい距離を置いてしまう
私は生活相談員として10年間、ご利用者とそのご家族と向き合ってきました。
そんな私も、初対面では今でも緊張します。
緊張しても、毎日無理なくコミュニケーションを続けられるようになったのは、
ある4つの工夫があるからです。
コミュニケーションは挨拶から、そして一言
コミュケーションの主役を利用者にする
コミュニケーションは短い時間でもよいと考える
短いコミュニケーションを積み重ねて信頼を築く
利用者はよくしゃべる方だけではなく、ときには気難しそうで口下手な方がいらっしゃいます。
そんな時、会話が弾まなくで気まずい雰囲気になって、困ったりすることがありますよね。
ポイントとして、第一歩は短い時間でも接点を自分から持つことです。
そして会話が続かなくても、盛り上がらなくても良いと考えることです。
具体的にお伝えします。
コミュニケーションは挨拶から、そして+1言
まずは挨拶をしましょう。
挨拶ができたら、そこに一言を添えます。
利用者とあった時に、最初にするのは挨拶ですよね?
(していない人も見かけますが、それはコミュケーション以前の問題です)
利用者との会話が~のまえに、しっかりと挨拶をしましょう。
挨拶に一言を付け加えると、関係づくりが一気に加速します。
挨拶は信頼構築の第一歩
最初に挨拶を明るいトーンでしましょう。
出会った時の挨拶の数秒で、関係づくりがほぼ決まります。
最初に出会って明るい挨拶ができたら、利用者から良い印象を持たれます。
そして良い印象は長期間に渡ります。
いわゆる初頭効果です。
私たちが誰かと初めて会う時、最初に交わすのが「あいさつ」です。この短い瞬間が、その後の人間関係に驚くほど大きな影響を与えることを、心理学では「初頭効果」(primacy effect)と呼んでいます。プリンストン大学の社会心理学者アレックス・トドロフ博士の研究によれば、人は他者に対して0.1秒という驚くほど短い時間で第一印象を形成し、その印象は長期間にわたって持続するという結果が出ています。
引用元:あいさつの印象が人間関係に与える影響 〜科学が明かす第一印象の力〜
つまり、最初の挨拶で良い印象を与えたなら、それがずっと続きます。
逆も然りで、悪い印象もあとに引きずるということです。
まずは自分から挨拶を印象よくしましょう。
信頼構築の一歩目です。
そして一言
挨拶をしっかりしたら、何か一言を添えましょう。
一言加えることで、利用者は「自分に関心を持ってくれている」と感じます。
その際にはできる限り、その方に特化した内容を添えましょう。
「今日は少し元気がないですね。大丈夫ですか?」
「髪型、変えましたね。よく似合っています」
「先週、家族との旅行は楽しかったですか?
利用者一人ひとりを見ていることが伝わり、相手もうれしくなります。
そこから関わり方が変わっていきます。
一言を添えて接するだけで、利用者との距離はぐっと縮まります。
ご利用者からの信頼を得ている職員は、挨拶の後に必ずその話題に触れます。
その時のご利用者の反応は、ほとんど全員が嬉しそうにします。
第一歩では、出会った時の挨拶から一言をプラスして、行動を変えていきましょう。
その一言は、会話の主役を利用者にすることにもつながります。
コミュニケーションの主役を利用者にする(質問をする)
コミュニケーションや会話が続くための方法としてよく言われているのが、相手の話を聞くことです。
そう、自分が話そうとするのではなく、ご利用者に話してもらうことです。
会話が苦手と思っている人は、自分が何かを話さなきゃと思っています。
私がそうでした。
そして、話すことに夢中になりすぎて、相手がみえなくなったのです。
退屈そうにしている相手の様子が、目に入っていませんでした。
自分語りになっていたのです。
大事なのは自分語りではなくて、利用者に「自分を語れる場」をつくることです。
語れる場があると、安心感と信頼感がうまれます。
自分:ご利用者=2:8程度の会話の割合をイメージしてみましょう。

話を聞くための質問
良質なコミュケーションはご利用者から、話を引き出していく質問が大事です。
質問で話を引き出すと、利用者は自然に心を開いてくれます。
次に関連する質問はおすすめです。
・季節や天気
・家族との近況
・体調や病気について
・趣味や過去の仕事
『季節や天気』
会話の入り口としては定番中の定番ですが、よく使える内容です。
・今、自宅には何の花が咲いてますか?
・今朝は寒くなかったですか?
他愛ない話ができる関係は信頼構築につながります。
『家族のこと』
子供のことや孫のこと、配偶者のことは誰かに話したくなる内容です。
・年末には誰か来るんですか?
・最近はお孫さんに会ってますか?
特に送迎などで会ったことのある家族の話は、質問しやすいです。
『体調や病気のこと』
年を取ると健康や病気の話が会話の中心になる。と聞いたことがあるかもしれません。
・今日は膝の具合はいかがですか?
・先日、病院では何か言われましたか?
医者と話したことなど、ノってくると嬉々として話してくれる方もいます。
『趣味や仕事のこと』
男性にとっては昔の仕事の話、女性にとっては子育てや趣味の話など、しゃべりだすと止まらないくらいです。
・昔のご趣味って何でしたか?
・仕事で大変だったことはありますか?
あらかじめ、何を質問するかを事前準備するのも良いです。
今日はこの利用者と会話してみようなど、ターゲットを決めておくとより行動しやすいでしょう。
話を聞く時の注意点
注意点は利用者を受け容れることです。
受け容れる行動とは
・否定しない
・アドバイスしない(求められない限り)
・自分の価値観を押しつけない
・共感は本当に共感したときだけ
そして、政治・宗教・戦争の話はできるだけ避けましょう。
話を聴く際には、注意しておかないとご利用者を不快にさせてしまうことがあります。
不快にさせてしまうとこちらも次回から、話しかけにくくなります。
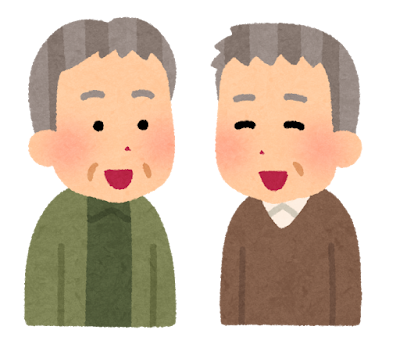
受け容れる
『否定しない』
誰でもそうですが、張り切って話をしているところに否定する言葉、
腰を折る発言が入ると話をする気が失せてしまいます。
決して否定的な発言はせずに、話しやすいように相づちを打ちましょう。
否定しないことで、話をしやすい雰囲気を作ってあげることです。
『アドバイスしない(求められない限り)』
解決策などのアドバイスをすることは、相手を慮っているようで逆効果です。
大半の人は、話を聴いてほしいだけです。
まして病気の話や家族の問題などは、他人がアドバイスできない内容です。
求められたなら別です。
求められていないアドバイスをしている時点で、寄り添えてことができていません。
何かを話しているときは、話しやすい相づちを添えましょう。
『価値観を押し付けない』
どんなに共感できない話でも、まずは受け容れましょう。
例えば、あなたが好きなものを頭から否定されてしまったらどうですか?
自分を否定された気になって、それ以上その人と関わりたくなくなってしまいませんか?
無理に共感する必要はないですが、まずは相手の話を理解することに徹しましょう。
間違っても「論破」などはしないでください。
必要のない怨恨を生んでしまいます。
「共感は本当に共感したときだけ』
話を理解するように言いましたが、無理に共感する必要はありません。
本当に共感できることを見つけたときに、心から共感してあげてください。
全くその気がないのに、共感したふりをしても相手には見透かされてしまいます。
お互いに共感できることがあった時に、距離が縮まったり信頼関係が生まれたりします。
政治・宗教・戦争の話はできるだけ避ける
この手の話は本当に個人の価値観が色濃くなる内容なので、できる限り避けましょう。
時にはご利用者同士でケンカに発展することもあるくらい、デリケートな内容です。
うまくコントロールできるようであれば、別の話題に切り替えることを勧めます。

コミュニケーションは短い時間で良い
長く続く会話が苦手なら、それでも大丈夫。
むしろ、「一言交わすだけで十分」と考えることで、気持ちが楽になります。
そうすると話をすることが、苦ではなくなります。
ほんのちょっと話ができただけでも充分と捉えて、積極的に話しかけましょう。
会話を続けることを目的としないことで相手の話に集中できる
あらかじめ会話を続かせようと思っていたら、そこに気を取られしまいます。
・次に何を質問しようか
・気の利く言葉は何か
次に何を言うか考えている時点で、会話に集中できなくなってしまいます。
相手の言葉に集中し、気持ちを理解しようとする姿勢は、相手に伝わります。
むしろ話していることに対して、即座に準備していた言葉を並べるほうが、本当に聞いてくれているか疑わしくなります。
まずは会話を続けることよりも理解することに徹しましょう。
必ず一言でも言葉を交わせば十分
最初に伝えたように、挨拶と一言で充分です。
会話をすることに抵抗がある人は、利用者を避けてしまうことがあります。
しかし、一度も接しないということは、利用者を無視した行動です。
人間関係において、好きの対義語は無関心です。
存在しないと扱われることは、とてもつらいです。
利用者にとって、一言でも言葉を交わすことは、自分の存在を肯定していると受け取られます。
一言だけでもいいので言葉を交わしましょう。
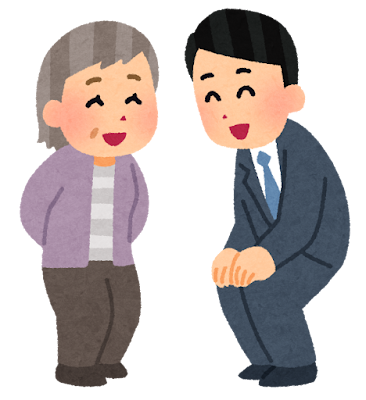
ちょっとしたコミュニケーションを積み重ねて関係を築く
「1日1回、言葉を交わすこと」から始めてみましょう。
どんな寡黙な方でも、毎日少しずつ接点を持てば、いつか心を開いてくれます。
実際、いろんな利用者に積極的に話しかけようとしている職員の姿を、利用者はしっかり見ています。
そういう職員には、自然と声をかけてくれるようになるんです。
1日に1回、接点を持つこと
まずは短い、ちょっとしたコミュニケーションでいいです。
その日に1回、その人と接点を持ちましょう。それでいいです。
そう考えると、話しかけること、話すことにエネルギーはいらなくなります。
それを毎回、続けていくことを積み重ねましょう。
一生懸命にコミュニケーションをとろうとしていることは利用者にも伝わる
少しでもいろんなご利用者に話しかける人
あるいは逆に話しかけやすい人にしか寄っていかない行動は利用者に見られてます。
いろんな人と、コミュニケーションをとろうとしている行動や気持ちを、継続しましょう。
続けていくと、必ずそれを見ているご利用者がいます。
そんな人には話しかけてくれるご利用者も増えてきますし、話を聴いてもらいたいと思われます。
そうなってくると自分で話をする意識をしなくても、自然と会話が成り立つようになります。
誰に対しても少しの会話を続けること、それをとにかく継続してみてください。
まとめ
ご利用者との会話が苦痛にならないためには、
コミュニケーションは挨拶から、そして一言
コミュケーションの主役を利用者にする
コミュニケーションは短い時間でもよいと考える
短いコミュニケーションを積み重ねて信頼を築く
このように考えて行動することで、会話が苦痛にならなくなります。
そして意識すれば、無理なく関係性を深めていけます。
介護の現場での会話は「心の架け橋」です。
あなたの一言が、利用者の一日を明るくするかもしれません。
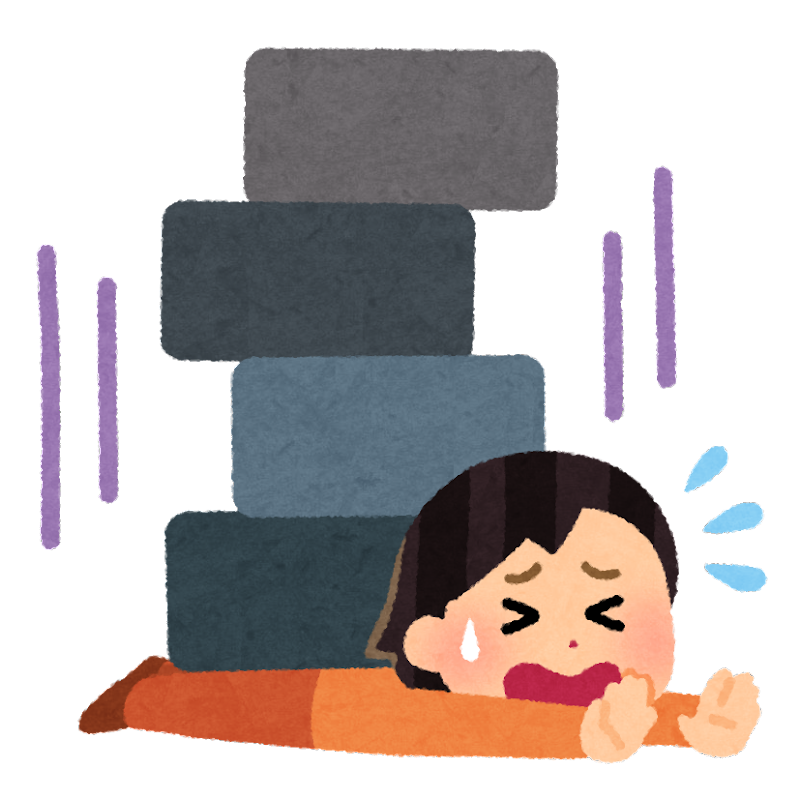

コメント